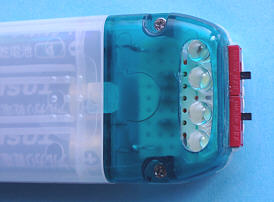4A_携帯電話用の充電器のケースに、LEDを4個入れる
4A_携帯電話用の充電器のケースに、LEDを4個入れる
 単四3本使用の携帯電話用の非常電源ケースを使い、
単三3本と単四3本なら、大きさ、重量でほぼ半分になるのかを考察。
単四3本使用の携帯電話用の非常電源ケースを使い、
単三3本と単四3本なら、大きさ、重量でほぼ半分になるのかを考察。
電池のみの幅は、43.5mmと31.5mm
電池のみ重量は、57~70gと27~33g
マンガン電池よりアルカリ電池の方が少し重い。
定電流化完成。動作良好です。
ケースに合わせて、基板と部品を考察する。

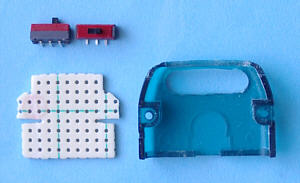 基板は、固定方法を考えて形状を決めます。
今回ははめこんだだけで、ビス止めは無しです。
基板は、固定方法を考えて形状を決めます。
今回ははめこんだだけで、ビス止めは無しです。
上のカバーは、LEDの窓と、スイッチの窓を加工します。 LEDの窓は少し外側へ広げます。
上部のスイッチ側は、全体に大きくします。 部材が小さいので、割らないように注意が必要です。
ケースは3個に分解できます。
最初に、下ケースの電話器とつなぐコネクターを外します。半田個所2箇所。
上のカバーの窓をカッターナイフで切り取り、ここからLEDを発光させます。
左右は少し広げます。
つまり、光線はケースに対して直角に出ます。
ポケットに入れて、頭を上に出すと、前方を照らします。
LEDを4個使う事にして、基板の形状を考え、加工します。
下ケースの当たる個所は充分注意して、加工します。
回路はLED2個とスイッチ1個を1回路として2回路使います。
スイッチ、LED、抵抗器など、必要な部品を調達します。
スイッチの足は直角に曲げて、基板から出した線に半田します。
つまり、足が短いので継ぎ足します。
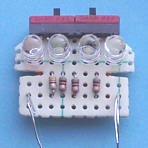
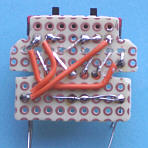
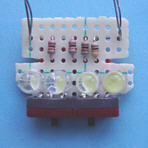

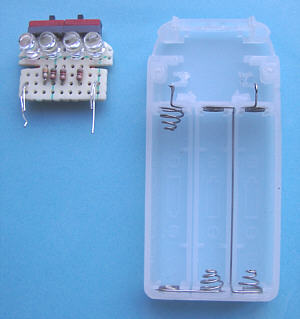
LEDとスイッチの間が狭いので、LEDのベースが当たる所を少しきります。
回路は、中央の2個と外側の2個に分けてスイッチへ接続します。
スイッチのつまみ位置は、間隔が狭いとき、断です。
つまり、上からつまみを摘んだ時に消灯します。
電池との接続に注意して配線します。右の絵の右側の上が+側です。
完成です


完成です。LED4個がうまく収まりました。
スイッチの部分も何とか収まりました。
長さが短いので、ポケットへ入れても、
うまい具合にはポケットからは頭が出ません。
電流の実測値はLED4個で90mAでした。
当初の希望道理か?
最初の考察道理出来あがったかの検証です。
共に、画像左:単四3本利用の懐中電灯、画像右:単三3本利用の懐中電灯


| 単四3本利用の懐中電灯 | 単三3本利用の懐中電灯 | |
| 形状 | 78(長)×35(幅)×16.5(厚み)mm | 72(長)×48(幅)×19(厚み)mm |
| 体積 | 45045立方mm | 65664立方mm |
| 重量 | 55g | 100g |
現物の見かけは、半分くらいかなと見えるが、実際には2/3が正解か?
回路図と消費電流です
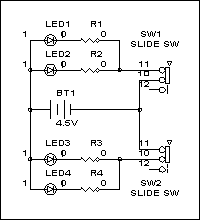
LEDを2個づつに分け、スイッチで点灯を切替えた。
消費電流は4個点灯時のものです。
これを見ると電池電圧が下がると、随分電流も下がるのが解るが、 人間の目は誤魔化せるので、多分3.5Vになっても使用に耐えるでしょう。定電流化を考察です
上記の表に示すとうり、電流が電圧の降下で低下するので光度が下がります。
これを電池電圧が3.5Vまで同じ光度を保つように考察します。
回路はオペアンプを使うと簡単ですが、基準電圧を作るのが課題です。
FETに電流を流すと定電流になるのでこれを使います。抵抗値で調整をしました。
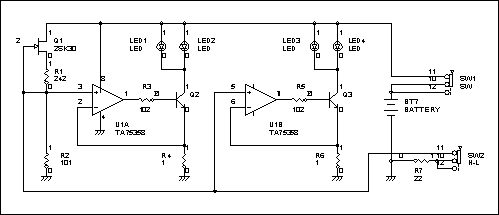
スイッチは電源スイッチを1回路と、
輝度を落とすモードにする切替えスイッチを1個の計2個です。
回路の動作は、トランジスタのエミッタ側の1Ωの抵抗の両端の電圧が、
オペアンプの+側の電圧と等しくなるように、常にトランジスタをドライブします。
LED2個分の電流はトランジスタを通り1Ωの抵抗に流れます。
オペアンプの+側の電圧を40mVにすれば、
1Ωの電圧も40mVになります。
1Ωの抵抗に40mAを流せば40mVです。
この様にしてLEDには2個で40mA流れます。
オペアンプの+側の電圧は100Ωの両端の電圧です。
100Ωと22Ωをパラレルに接続すれば、
(100×22)/(100+22)=18Ωです。
この両端の電圧は7.2mVです。
同じ回路が2回路ありますので、通常は80mA、
モードを切り替えると14.4mAです。
完成です


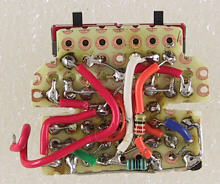
基板を外し、回路を組込みます。左から、上から、横から、裏側です。
部品が多くて大きいので、足を2本まとめて差し込んだり、苦闘の跡が偲ばれます。
何処にも部品の頭が当たらないように高さに注意して作ります。
LEDの底部と基板上に、反射塗料を塗りました。
雲母マイカと
アルミニュウム粉末が入っているマニキュアを100円で手に入れ塗ります。


回路が動いたら完成です。元の場所に収めます。 さて、動作電流はどうなるか、楽しみです。
消費電流です
定電流化が考察道理出来あがったかの検証です。 定電流化完成。動作完璧です。
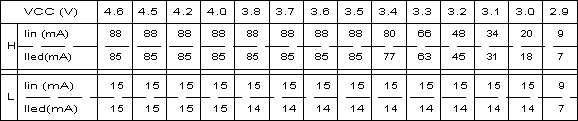
左端のHは通常の電流。Lは低消費電流の時です。
スイッチで光度が切替えられます。
これを見ると、電池電圧4.5Vから3.5Vまで定電流であり、
最初の考察道理に出来あがったことが解ります。
Lの場合は、3.0Vまで同じ光度を保ちます。
Lの時の電流値を45mAに設定すれば、電池電圧が3.2Vの時に、
同じ光度になり、明るさを切替えても光度が変化しなければ電池の交換時期です。
と言う使い方も出来ますが、低消費電流とは言えず、どうするかは課題です。
-
画像の色が前半と後半で違うのは、照明とカメラが共に違う為です。
明るさは、400Lux(25cm)でした。
明るさは、400Lux(25cm)でした。